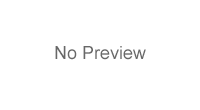(ニュースから)なぜ、医者は自分では受けない治療を施すのか
なぜ、医者は自分では受けない治療を施すのか – 萬田緑平
http://blogos.com/article/111515/
医者は自分では絶対に避けるような多大な困難をともなう治療を患者に施術することがある。私たちは病気になって焦る前に考えておかなければならないことがあった。
なぜ、医者は自分では受けない治療を施すか
医者も人間ですから、必ず病気になります。当然、がんに罹る可能性もあります。
しかし多くの医者は、自分が病気になったとき「やらないほうがいい治療法」があること、そしてその多さを認識しているはずです。
もちろん患者さんの年齢やがんの種類、ステージなどケース・バイ・ケースでしょうが、治癒の見込みがきわめて困難な場合、患者が医者自身ならば抗がん剤治療を行わないケースが多いのではないか。ぼくもそうですし、医者仲間とも、「抗がん剤治療は勘弁してほしい」「この手術だけは絶対にしたくない」などと話すことがあります。闘病のつらさ、苦痛、日々疲弊していく患者さんの表情、身体――それらを日常的に目の当たりにしていて、ある程度は見通しがつくからでしょう。
平たく言えば、自分と自分の身内には、すすめられない治療がある。しかし患者さんに施している可能性がある、ということです。
では、患者に抗がん剤治療を施す医者は不誠実なのかというと、そう短絡的な問題ではありません。
実は真面目で誠実な医者ほど、つらい治療を患者さんに強いてしまうことがあります。結果、いわゆる延命治療になりがちなのです。
なぜ、医者はつらい治療を患者に施すのか。大きく分けて2つ、理由があると考えます。
まずは医者側の問題。
病気を治す、というのが医者の当然の役目ですから、全知全能全人格を使って治療することが前提です。
医療報酬やら薬の投与点数やら手術の実績やら、病院や医師が利益を得るような構造上の問題も多少は横たわっているとはいえ、基本的には医師は真面目で律儀で優秀な人が多いから、「治すことがわたしの使命だ」と考えます。
その一方で、「治療をやめるとどうなるのか」ということに医者は無知です。
医者が患者さんに治療法を説明するとき、“エビデンス”という言葉を使います。治療法が優れているとされる科学的根拠のことです。医者はエビデンスのある治療を受けた患者さんがどうなるのかは知っていますが、受けなかった場合や治療をやめたケースで患者がどうなるのか――をよく知りません。そういう教育は受けてきていないし、病院では治療継続という形でしか患者さんに接することができないからです。だから、進むしかないわけです。
2つ目は、患者さんの家族です。延命治療の弊害の一因は「家族」です。そして、患者さんが幸せな最期を迎える鍵も家族が握っていると、ぼくは思っています。
家族は、心から患者さんの治癒を願います。患者さんには「頑張れ!」と励ましの言葉を送り、医者には「なんとか、助けてください」と懇願する。患者の容体を心配する家族。ごくごく当たり前の関係性です。
患者さん、医者、そして家族がそれぞれ頑張り、現代の医学をもってすれば、きっとなんとかなる。優秀な先生がきっとなんとかしてくれる。多くの家族が、そんな希望の灯を胸にともします。この希望の灯は強く、メラメラと燃えています。
そう懇願されれば、医者は当然治療を施します。意気に感じる医者は少なくない。面目躍如でしょう。もし仮に、「これ以上は患者さんが苦しむだけです。抗がん剤治療をやめましょう」と提案したとしたら、「見放された。医療の放棄、怠慢だ」などと非難されかねません。いきおい、医者は家族の意向に従わざるをえません。そういう関係性は容易にできあがります。
要するに、患者さん本人よりも家族の願いが中心になっていく。患者さんがあまり強い意志を持たない高齢者の場合は特に顕著で、「家族の嘆願」→「それを受けた医師の治療」→「患者の疲弊」という流れに陥りがちです。そういうことが数限りなく繰り返されてきています。
患者さんに治療の理解を深めてもらうために、ぼくはいろいろな喩えを使います。
殺伐とした言葉の響きですが、治療は“戦争”です。闘病という言葉はまさに言い得て妙で、戦争をイメージさせるものですね。
患者さんは国王。身体は国土です。内臓や血液などの器官が国民。そして、医師は将軍です。手術や薬は爆弾やミサイルなどの武器ということになります。
では倒すべき敵は……がんなどの病気です。
敵が国土に攻め込んでくる。国土を荒らし、国民を蹂躙している。それを黙って見ているわけにはいきませんから、国王は将軍に抗戦を命じ、身体が臨戦態勢になります。戦争の専門家である将軍は、さまざまな手を駆使して敵を倒そうとします。
結果、敵が退散して元の平和の状態に戻れば勝利です。
抗がん剤の効果を副作用が逆転する時
しかし、勝てる戦争ばかりとは限りません。国家は未来永劫、続く可能性もありますが、人間の身体はいつかは必ず滅びます……。つまり、いつかは必ず負け戦を経験するのです。
戦局が決し、もう勝ち目がないという状態になった場合、将軍が武器や爆弾を使い続けたらどうなるでしょう。戦地である国土はさらに荒廃し、国民はどんどん死んでいき、犠牲が増大します。しかし専門家である将軍は「負け戦なので、降伏しよう」とは宣言し疲弊しきっているのならば、戦争をやめればいい。戦時体制を解くこと。つまり将軍のもとを離れることです。
もちろん、治療を全否定するつもりはありません。これまで、ぼくも将軍(外科医)として、散々戦ってきました。勝った戦もあれば、負けた戦もありました。そもそも戦うべきではなかったと後悔する治療もあります。
つらい例を挙げますが、「もう、こんなつらい治療はたくさんだ。家に帰りたい」と暴れるからベッドに体幹抑制されて、点滴を抜かないように縛られて、それでも騒ぐと鎮静剤を打たれて、そして意識障害に陥って……そうやって亡くなっていく。
家族は患者さんのためを思い、医師はその期待に応えようとしているのに、最悪の結果になってしまう。
悪循環を断ち切るのが、ぼくの立場、「在宅緩和ケア医」です。
緩和ケアというのは、死に直面した患者さんや家族の心身の痛みを予防したり和らげたりすることを意味しますが、ぼくは「最期まで自宅で暮らしたい」と願う患者さんのお宅に伺ってケアをしています。ぼくの患者さんの多くはがんを患っていますが、ぼくはがん治療をしません。「治療を諦めるのではない。治療をやめて自分らしく生きるんだ」というのがぼくのモットーです。
わかりやすく言うと、病院で闘病している患者さんに帰宅してもらう。
患者さんが自宅に帰ることについて、病院関係者は、「患者は病院でこれだけつらそうなんだから、家に帰ったらもっとつらいだろう」と思ってしまう。でもそれは想像力不足。患者さんにとって、病院はいわばアウェー(球技等での対外試合)で、自宅は(文字どおり)ホームです。確かに医療環境は劣るかもしれませんが、家のほうが心身ともにリラックスできます。私の経験では70歳の患者さんで7割、80歳で8割、90歳で9割と、高齢になるにつれて家で過ごしたくなるようです。
患者さんの帰宅には、家族の理解が不可欠です。「もう、つらい治療を続けなくてもいいんだよ。頑張らなくていいんだよ」と家族が思えば、「家族の嘆願」→「治療の継続」→「患者の疲弊」という悪循環を断ち切ることができます。
しかし、家族も納得して、患者さん本人も苦痛ばかりで治療を終わらせて家に帰りたいと思っているのに、それが叶わないことも多々あります。
あくまでも退院を許可したくない医者
ぼくは家に帰りたいという患者さんの切望を叶えるべく、家族の要請を受けて、病院の主治医に退院の段取りを交渉することもあります。
がんが脳に転移して意識状態が悪化し、余命一週間とされて、転落防止のためにベッドに縛り付けられていた男性がいました。「家に帰りたいですか」と聞くぼくに、彼ははっきりと「あんたら、助けに来てくれたんか?」と言いました。そして、「水をたっぷり飲みてえ~。なんで縛られてんだか、わかんねえ~。ゆっくり風呂に入りて~」と嘆きました。死を目前にし、鎮静剤を打たれて朦朧とする意識の中で絞り出した叫びです。それを目の当たりにした家族はベッド脇で大泣きしました。
しかし、ぼくが直接交渉した主治医はあくまで首を横に振ります。「こんな状態では退院させられない。まだ治療が必要」と。ぼくは、この医師に嫌われてもいい、悪評を立てられても構わないと決心し、強い口調で抗弁しました。
「治療を続ければ亡くならないのですか? あと何日命が延びるのですか? 本人やご家族は退院を希望しているんですよ」
主治医はしぶしぶ退院の許可を出しました。患者さんは自宅に戻り、点滴も尿カテーテルも取り払い、水どころか晩酌も楽しみ、4回目の訪問入浴のあと、家族に見守られて眠りにつきました。退院から約2週間後のことでした。
家族が患者さんのつらさを慮れば、延命治療の悪循環は断ち切られるわけですが、病院の医者も意識改革をするときだと思います。この10年くらいの間に、緩和ケア外来や病棟を創設した病院や、各科の垣根を取り払った緩和ケアチームをつくるなどの動きが増えてきています。それでもまだまだ、という気がしてなりません。
医者たちは頭ではわかっている。自分や自分の家族には施したくない治療があると認識しているんですから。大病院が意識改革に本腰を入れてその気になれば、立派な緩和ケアチームをつくることが可能なのです。
(一定期間が過ぎると消えてしまう有用なニュースを掲載しています。)